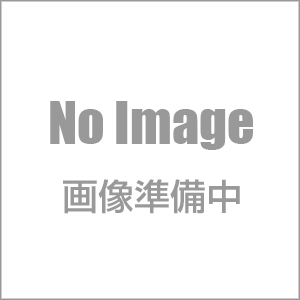拝啓
時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素より格段のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
さて、魚価や諸経費の値上がりにより、弊社でも吸収するべく努力を重ねてまいりましたが値上がり幅は大きく、
企業努力のみでは吸収することが大変厳しい状況となっております。
つきましては、以下の商品価格の改定を3月1日より実施させていただくこととなりました。

今回の価格改定でお客様のご負担が大きくなってしまいますことを
心よりお詫び申し上げるとともに、何卒ご理解をいただき、
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。